
2025年4月
仁科記念財団理事長 梶田隆章
仁科記念財団は1955年に創設されました。2011 年4月1日には,新しい公益法人制度のもとで認定を受けた公益財団法人となり,以来新たな歩みを進めております。 その定款には財団の目的を「故仁科芳雄博士のわが国及び世界の学術文化に対する功績を記念して,原子物理学及びその応用を中心とする科学技術の振興と学術文化の交流を図り,もってわが国の学術及び国民生活の発展,ひいては世界文化の進歩に寄与すること」と謳っております。この目的を達成するために,仁科記念賞の授与,仁科記念講演会の開催,仁科記念室の運営,出版物の刊行などを中心的な事業と位置づけて実施しております。
仁科記念賞は,1955年度の第1回から2024年度の第70回までに203名の方に差し上げ,広い意味の原子物理学の分野におけるわが国の代表的な学術賞としての地位を確立しているものと思います。この間、仁科記念賞受賞者からのノーベル物理学賞受賞者は6名、文化勲章受章者は14名、文化功労者は21名、学士院賞(恩賜賞を含む)受賞者は36名になりました。また2016年末には,2005年度の仁科記念賞受賞者森田浩介博士を中心とするグループが提案した113番元素「ニホニウム Nh」が認められ,日本で発見された元素が初めて周期表に載りました。新元素の発見は,仁科博士が93番元素(ネプツニウム)の発見にあと一歩のところまで迫ったという歴史もあり,仁科記念財団にとりましては記念すべき出来事であります。
また毎年開催しております仁科記念講演会も多くの方から親しまれ,その内容を記録した出版物も好評を得ております。さらに仁科先生の残された多くの資料の整理公開も財団の任務でありますが,その一環として,元常務理事の故中根良平先生をはじめとする編者の皆さまの努力の結実であります「仁科芳雄往復書簡集」全3巻および補巻がみすず書房より出版されております。しかし、これらの資料が保存されていた建物が老朽化で解体されました。このため,2019年, 資料類は先生の愛用されていた調度品と一緒に理研和光事業所に寄附されました。
財団は海外の研究者との交流も支援してきており,2012年度に,アジア地域できわめて優れた成果を収めた若手研究者を顕彰し,わが国の研究者との交流を深めていただくことを目的として,Nishina Asia Award (仁科アジア賞) を創設いたしました。過去10年間、傑出した業績を挙げたアジアの若手研究者を顕彰してきましたが、2022年10月27日に開催された第40回理事会にて、Nishina Asia Award は所期の目的を達成したと判断し、この事業を終了することに決定し、2024年度をもってNishina Asia Awardに関する全ての活動を終了いたしました。
仁科先生は1921年に渡欧され,1928年に帰国されましたが,その大半の期間,コペンハーゲンのニールス・ボーアのもとでご研究をされました。まさに量子力学成立の時期に,その中心地で活躍されました。当初はX線分光の実験的研究をされていましたが,ご帰国直前には,理論研究に転じて,有名なクライン・仁科の公式を発表されました。これは自由電子と光子の散乱断面積を与える公式を導いたものですが,ディラックの空孔理論の成立にも大きな影響を与えたと推測されます。こうした歴史的な研究の進展を目の当たりにされた先生は,ご帰国後,大きな夢を抱いて理化学研究所の仁科研究室を主宰されたものと思われます。仁科記念財団は仁科芳雄先生の理想を受け継ぎ,わが国の基礎科学の進展に貢献することを使命としていると考えます。皆さまのご支援を得つつ,微力を尽くしてまいりたいと思います。
理事長略歴
梶田隆章(仁科記念財団第7代理事長:2023―)1981年埼玉大学理学部物理学科卒,専門は宇宙線物理学。1998年,ニュートリノ国際会議でスーパーカミオカンデ実験によるニュートリノ振動の証拠を報告した。 1999年,「大気ニュートリノ異常の発見」により仁科記念賞(第45回)を受賞。2015年,「ニュートリノに質量があることを示すニュートリノ振動の発見」によりカナダ人のArthur B. McDonaldと共にノーベル物理学賞を受賞。2015年文化勲章受章。東京大学卓越教授。第25期日本学術会議会長。(1959―)
仁科記念財団歴代理事長
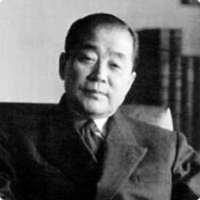
渋沢 敬三(仁科記念財団初代理事長:1955 – 1963)
渋沢栄一の孫。東京帝国大学経済学部卒。財界関係では日本銀行総裁,大蔵大臣,国際電信電話社長,文化放送会長などを歴任。生物学や民族学の研究者でもあり,日本民俗学協会会長,人類学会会長などを務めた。(1896 – 1963)

朝永 振一郎(仁科記念財団第2代理事長:1963 – 1979)
1929年京都帝国大学理学部物理学科卒,1932年理化学研究所仁科研究室に入所。日本の理論物理学振興の祖である。1952年文化勲章受章。1956年東京教育大学学長。1965年にシュウィンガー,ファインマンと量子電気力学分野の基礎的研究でノーベル物理学賞を共同受賞。(1906 – 1979)

久保 亮五(仁科記念財団第3代理事長:1979 – 1995)
東京帝国大学理学部物理学科卒。専門は統計物理学,物性科学。1953年に「久保―冨田理論」と呼ばれる,磁気共鳴現象の量子統計力学の定式化を行い,1957年にこれを一般化して「久保公式」といわれる線形応答理論を体系化した。1957年,「非可逆過程の統計力学」で仁科記念賞(第3回)を受賞。東京大学名誉教授。1973年文化勲章受章。(1920 – 1995)
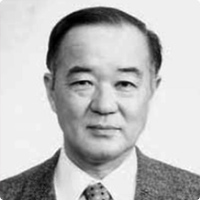
西島 和彦(仁科記念財団第4代理事長:1995―2005)
東京大学理学部物理学科卒。専門は素粒子論学。1953年,27歳のときに「西島―ゲルマンの規則」により素粒子の新しい規則性を発見。1956年,「素粒子の相互変換に関する研究」で仁科記念賞(第1回) を受賞。東京大学および京都大学名誉教授。2003年文化勲章受章。(1926 – 2009)

山崎 敏光(仁科記念財団第5代理事長:2005 – 2011)
東京大学理学部物理学科卒。専門は原子核素粒子物理学。1970年,理化学研究所サイクロトロンを用い,重い原子核の高スピン磁気モーメントの測定から,陽子の軌道磁気モーメントの異常増大を見出す。1975年,「核磁気能率に於ける中間子効果の発見」で仁科記念賞(第21回)。東京大学原子核研究所長,同名誉教授。2009年文化功労者。(1934 – 2025)

小林 誠(仁科記念財団第6代理事長:2011 – 2023)
1967年名古屋大学理学部物理学科卒,専門は素粒子理論。1973年,益川敏英と共に CP 対称性の破れに関する小林·益川理論を提唱した。1979年,益川と共に「基本粒子の模型に関する研究」で仁科記念賞(第24回)を受賞。2008年,「クォークが自然界に少なくとも3世代以上ある事を予言する,CP 対称性の破れの起源の発見」で益川と共にノーベル物理学賞を受賞。2008年文化勲章受章。高エネルギー加速器研究機構特別栄誉教授。(1944―)
